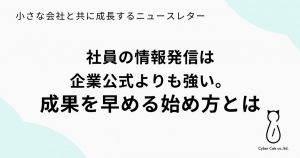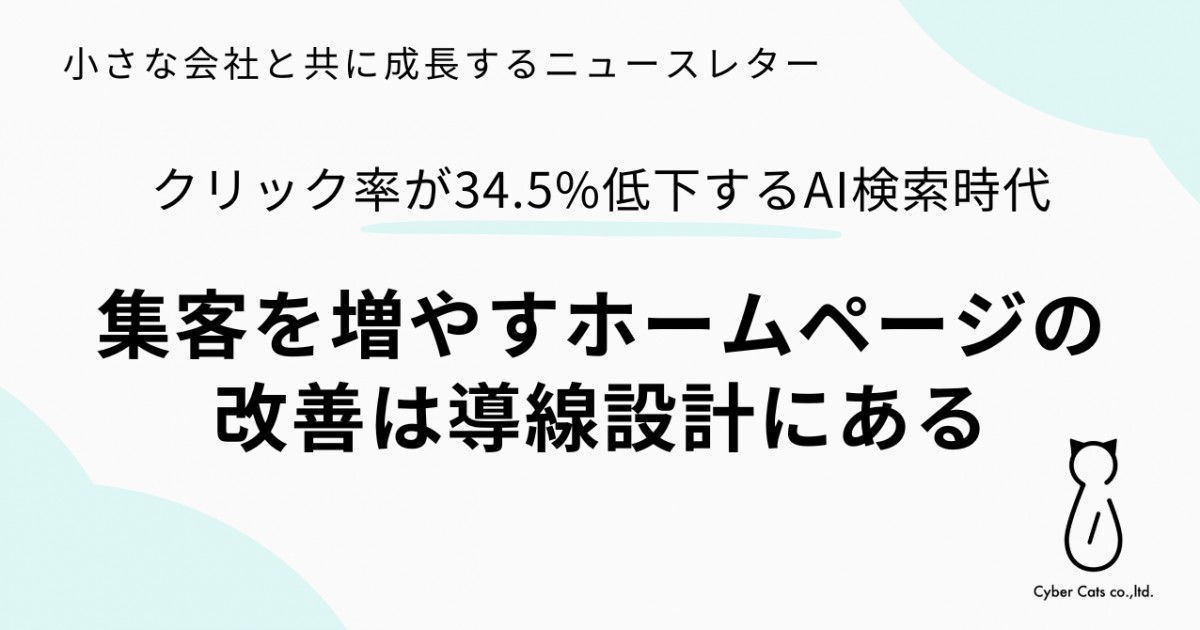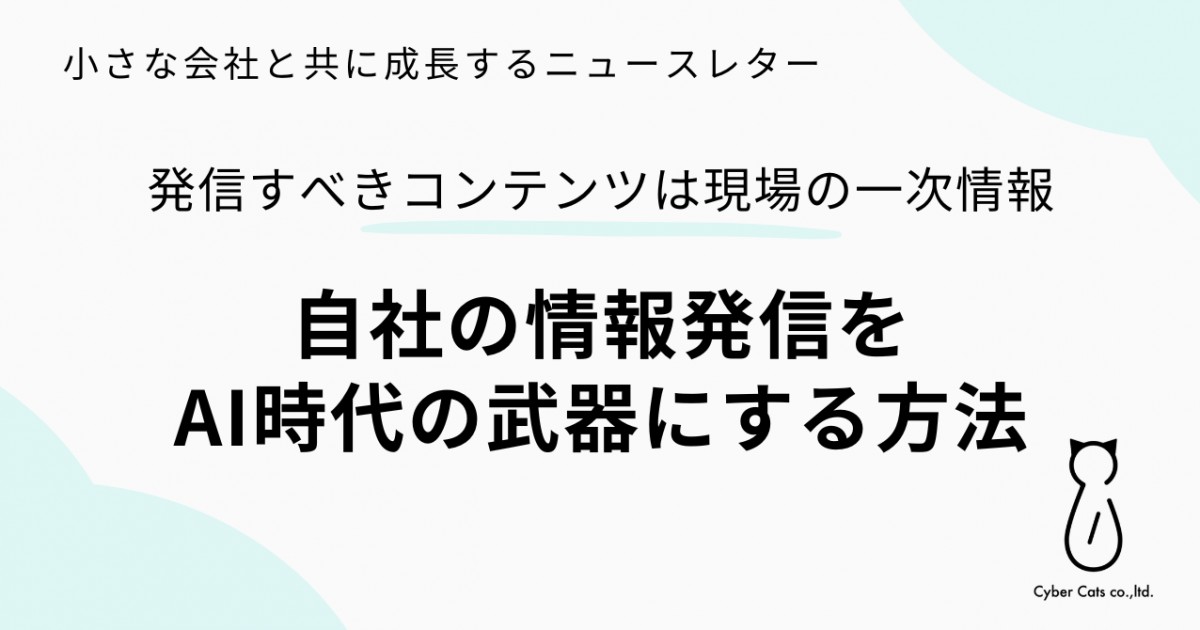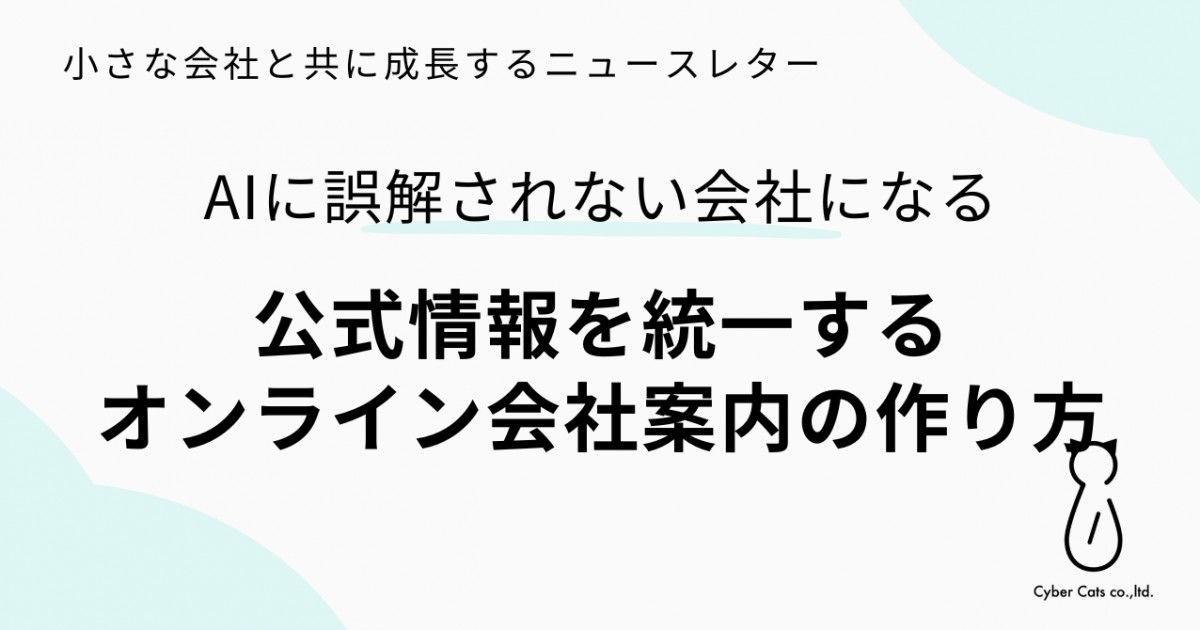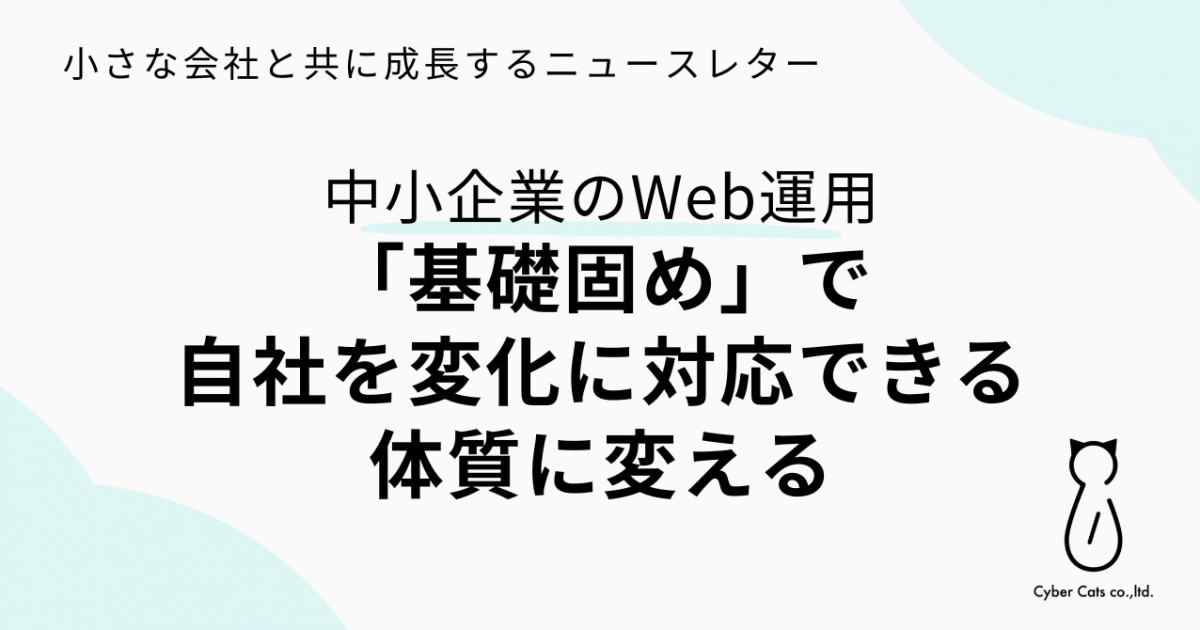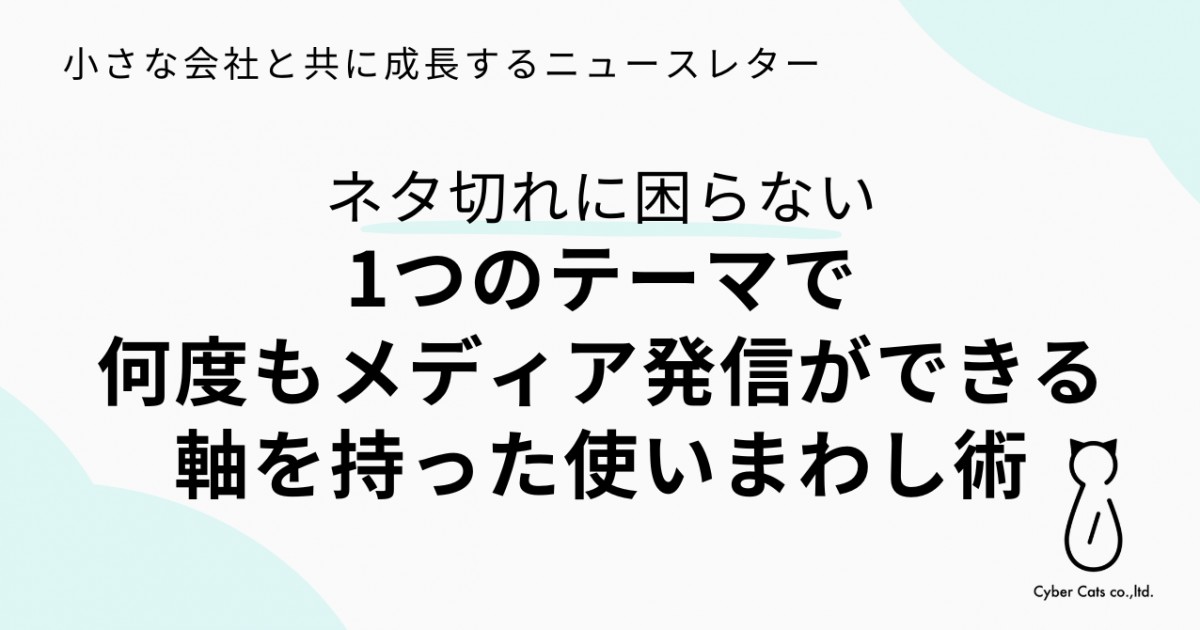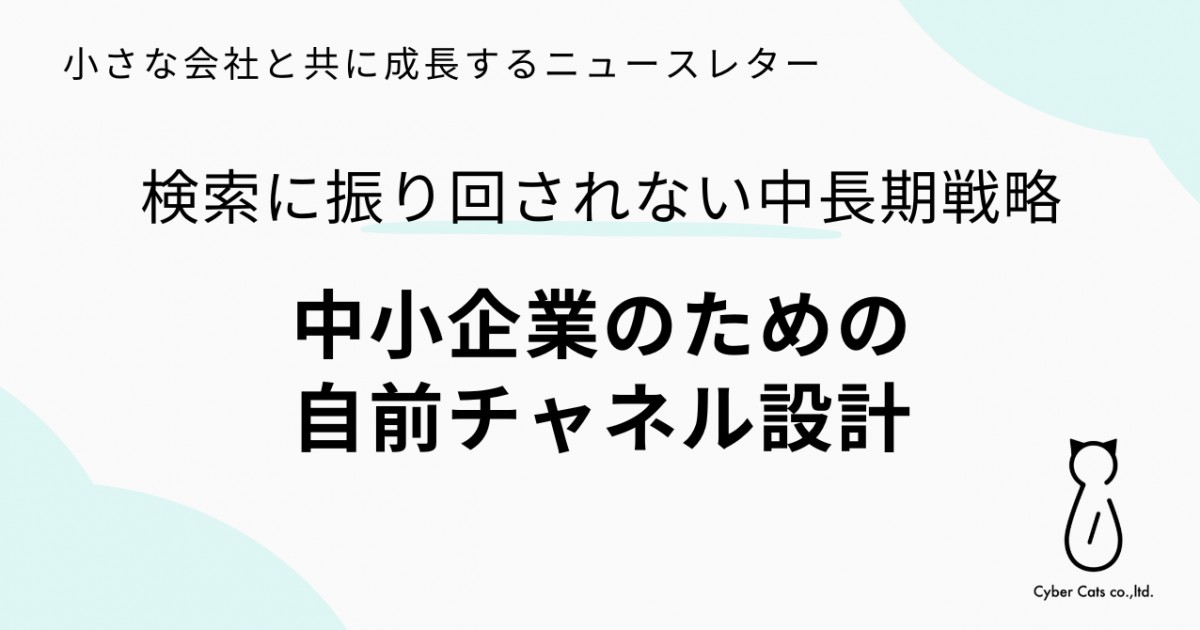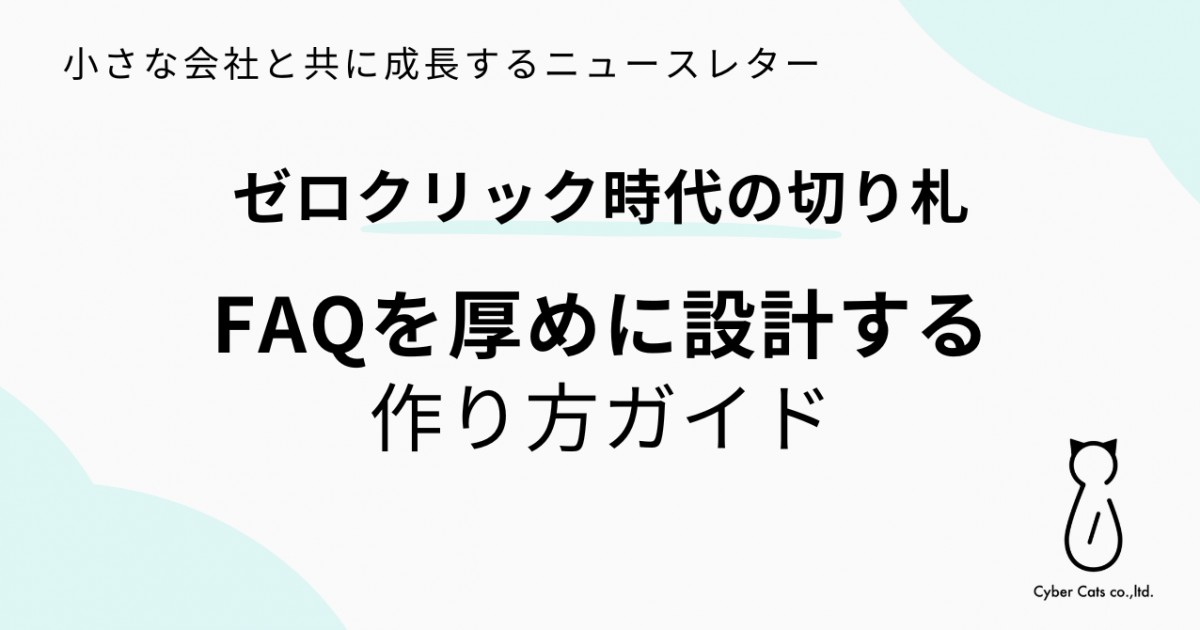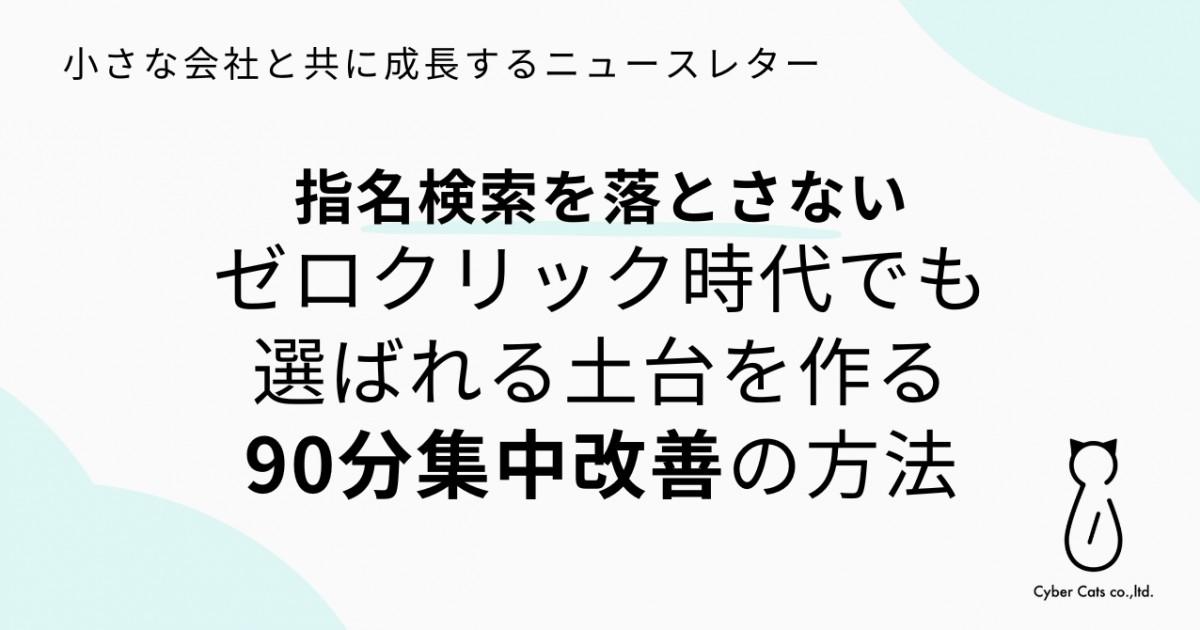公式より刺さる。社長の情報発信が採用・社内・営業を強化する理由と始め方
こんにちは、チャコウェブの横山ゆみこです。
公式アカウントからの一方通行なお知らせだけでは、なかなか心は動きません。
一方で、社長自らが顔と名前を出してSNSで情報発信すると、企業への求心力が高まるケースが増えています。
実際、X(旧Twitter)などでは、社長自ら発信して注目を集める例が見られます。
とはいえ、多くの経営者にとってSNSで発信するのはハードルが高く、「もし失言したら…」という炎上リスクへの不安も大きいのではないでしょうか。
今回は、社長自身が発信することで得られる総合的な効果について、社長の心理(なぜ発信が苦手なのかという背景)にも触れながら解説します。
前回は社員、今回は社長と続いています。
「え、そんなに要るの?」
「中小企業なんてそこそこの発信ができれば十分では?」
こんな風に疑問に思うかもしれませんが、むしろこれまでが発信不足だったと私は考えています。
なぜなら発信量を増やすことで集客や採用に成功している事例を多数知っているからです。
その方たちも、最初は「そこまでしなくても良いのでは?」という考えでしたが、今では積極的に発信する側に立っています。
前回のメンバーの個人発信をする効果と仕組みづくりとぜひ一緒にご覧ください。
目次
🤝 企業より人(社長)を信頼するのが現代の私たち
📣 社長の発信は公式アカウントより影響力を持つ
💭 社長の言葉が届かない・伝わらない3つの理由
🧯 失敗や炎上を恐れすぎていませんか?
🚀 社長発信で得られる3つの効果(採用・社内共感・営業強化)
⚙️ 社長が発信を始めるためのポイント
⚠️ 発信リスクへの向き合い方
📌 まとめ
🤝 企業より「人(社長)」を信頼するのが現代の私たち
そこそこの情報はどこでも手に入る今、「誰が語るか」が結果を左右するようになりました。
企業公式アカウントは、機械的な感じ、無機質なイメージを与えがちです。
そんな中では、顔が見える個人の言葉は信頼を集めます。
特に企業の代表が発言すると、会社の想いにも重なり、影響力が増すのです。
ある調査によれば、企業公式サイトに次いで消費者や求職者が参考にするのは、社長のSNSでの発信だというデータもあります。
また、消費者の93%が「社長がSNS上で積極的に発信することは企業イメージを形成する」と考えています。
社長の発信がある企業とない企業では、社内外からの見られ方に大きな差がつくということですね。
📣社長の発信は公式アカウントより影響力を持つ
実際、リーダー(経営者)の発信内容は企業公式よりエンゲージメント(反応)が高いことが分かっています。
経営陣による投稿は企業アカウント投稿の2倍のエンゲージメントと3倍のコメントを集めたとの報告があります。
社員がシェアした投稿が企業公式アカウントの8倍以上の反応を生んだという報告もあり、人(社員や経営者)の発信力は企業ブランドそのものより強力なのです。
企業公式アカウントが何万人フォロワーを抱えていても、社長本人の発信がそれ以上の反響を呼ぶことも珍しくありません。
老舗石鹸メーカー・木村石鹸の木村祥一郎氏はX上で積極的に発信し、自社の理念や商品開発の舞台裏を率直に語っています。
その発信内容に共感したフォロワーから多くの反応が寄せられています。
抱えている課題意識なども見えるので、社長の発言を通して企業を知ることができ、つい見てしまうのではないでしょうか。
私自身、特にXのようなテキスト中心のSNSでは「社長さん自らが名前・顔出しで発信すると効果が高いですよ」と日々お伝えしています。
人はブランドロゴよりも中の人を信じるもの。
経営トップの声ほど心に響くメッセージはないのです。
💭 社長の言葉が届かない・伝わらない3つの理由
そうは言っても、
「本当に社長の言葉って意味があるの?」
「発信してみたけれど反応がない…」
という悩みもよく耳にします。
社長の言葉を発信する顧問編集者竹村俊助氏は、著書『社長の言葉はなぜ届かないのか?』で社長のメッセージが伝わらない原因を3つに分類しています。
届ける気がない
「情報発信は広報やメディアの役目。経営者は経営に集中すべき」
このように考え、最初から自分の言葉で伝える意志がないというものです。
昔はそれでも良かったかもしれません。
しかし今は経営者自身が前に出る時代だと竹村氏は指摘します。
社長が発信しない会社は、それだけで時代に取り残されつつあるのです。
書籍で語られている求職者の行動は、実際に弊社が支援している企業に応募した方と同じものでした。
-
求人サイトでいくつか気になる会社をピックアップ
-
社名で検索し、公式ホームページを見る
-
SNSで検索し、企業アカウント、社長アカウントの発信を見る
-
社長の発信内容に共感し、応募する
もし、社長の発信がなければ、他社との比較で応募まで至らなかったかもしれません。
伝え方がつまらない
社長が勇気を出して発信しても、「企業っぽい当たり障りない内容」では心に響きません。
わざわざ社長のアカウントを見に行くのは、こんな情報を望んでいるからです。
-
どんな想いで経営しているのか感じたい
-
社長個人の人柄を見たい
-
事業に関することや組織に関することへの考えを知りたい
社長個人の想いが感じられず会社が主語になっている投稿、無味乾燥な情報の羅列ではスルーされてしまいます。
各方面に気を遣いすぎたり、成功談ばかり語ったりする発信は退屈になりがちです。
「こんなに素晴らしいビジョンがあります!」
といった発信だけでは人は動かず、なぜそのビジョンに至ったのかという、原体験や葛藤を語る必要があるのです。
届け方が不適切
メッセージそのものは良くても、使う媒体や形式が間違っている場合もあります。
社内向け新聞にひっそりと社長ブログを載せても、当然ですが読めるのは社内のスタッフだけ。
就職活動中の学生や取引先には届きません。
広く不特定多数に伝えるには、オフィシャル感が強すぎない場所で社長個人が語るのが効果的です。
🧯失敗や炎上を恐れすぎていませんか?
「社長の発信なんて自分には無理だ…」
と感じている経営者も多いでしょう。
聞いてみると、消極的になる理由は以下のようなものがありました。
-
SNSの炎上を取り上げているニュースを見て警戒している
-
既に他の人が素晴らしい発言をしているので、自分のつたない言葉では意味がないと思ってしまう
-
SNSの経験がないので気後れしてしまう
皆初心者からスタートしている
ご安心ください、最初は皆さん初心者です。
本当に伝える気さえ持てば、文章やSNS運用のスキルは後から磨くことができます。
LINEヤフーの会長、川邊健太郎氏は「今からは情報発信が何より大事」と、10万人フォロワーを達成するまでコツコツと有益な情報発信を続けたことで有名です。
これだけ大企業のトップでも努力し続けてようやく発信力が身に着いたということですから、私たちのような小さな会社が最初から成功するとは思えませんよね。
「自分は文章が苦手」という社長でも、社内の広報担当者や外部パートナーにインタビュー形式で話を引き出してもらい、それをまとめてもらう方法もあります。
つまり、「伝える気さえあれば手段はある」のです。
あとは社長自身が腹をくくって一歩踏み出すかどうか。
次章では、そうして社長自ら発信を始めたときに得られるメリットを見てみましょう。
🚀 社長発信で得られる3つの効果(採用・社内共感・営業強化)
社長が自ら発信することで得られる効果は多岐にわたります。
「経営者の発信は、営業・広報・採用・ブランディング・社内コミュニケーションなどあらゆる方面に影響する、最もレバレッジの効く施策だ」
先にご紹介した竹村俊助氏はこのように述べています。
ここでは特に重要な以下の3点に絞って紹介します。
採用強化(自社に合う人材の獲得)
海外の調査ですが、「経営者自身がSNSで発信している会社で働きたい」
と考える従業員が80%にのぼったと報告されています。
日本でも同様で、企業が人材に「選んでもらう」時代において、社長からの情報発信はもはや不可欠です。
実際に、Xで社長の日々の考えや会社の文化に触れて共感して入社してくる人は、入社後のミスマッチも少なく即戦力になりやすいと言われます。
例えば精密加工業の栗原精機では、社長が「おやっさん」の愛称でXに登場し、自社の職場の様子や想いを発信しています。
それを見た若者が「この社長の下で働きたい!」と共感し、SNS経由での採用に成功した例もあります。
社長の言葉に共感して応募してきた人材なら、入社後も会社の理念を体現してくれる可能性が高いですよね。
社内への共感形成(社員のエンゲージメント向上)
社長がオープンに発信する姿勢は、社員との信頼関係構築にもつながります。
営業の方や販売担当の方はこのような経験をしている方がいます。
「御社の社長さんのSNS、よく見ていますよ」
取引先からこんな言葉を掛けられることもあり、「自分も見ておかなければ」とより一層自社の社長の発信をみる習慣がつくそうです。
経営トップが自ら情報発信している会社では、社内でも
「社長は本音で語ってくれている」
「ビジョンに共感できる」
という声が増えるのです。
実際、木村石鹸の木村氏は「会社やブランドのことを知ってくれる人が一人でも増えたら嬉しい」という想いでSNS発信を続けています。
「会社のこと、経営のこと、これからのことを一番知っているのが社長であり、一番発信しやすい立場です」と述べています。
営業強化(顧客からの信頼・売上向上)
社長が顔を出して発信することは、顧客や取引先からの信頼獲得にも直結します。
「経営者が積極的に情報発信している企業から購入したい」と考える消費者は全体の77%にも上ります。
中小企業でも、社長の発信がメディアで話題になり結果として商品の売上増や新規取引につながった例は多々あります。
木村石鹸の木村氏が発信することで、「社長のVoicyやXを聞いて商品に興味を持った」というお客様の声が増え、ブランド全体のファン層拡大に貢献したそうです。
社長自身が自社製品・サービスへの想いを語ることは、最安の広告でありながら最も説得力のある営業施策と言えるでしょう。
私も、SNSで社長が発信していることがきっかけでその企業のことが気になり、購入したことがあります。
⚙️ 社長が発信を始めるためのポイント
「よし、発信する価値は分かった。でも具体的に何をどう発信すれば…?」
と戸惑う方に、押さえておきたいポイントを整理します。
会社ではなく「自分の言葉」で語る
社長が発信する際は、「会社の公式情報」ではなく社長個人の視点と言葉で語ることが重要です。
事実ベースのニュースリリースは広報に任せます。
SNS上では肩書を外し一人称で思いを語る方が圧倒的に響きます。
「弊社は〜」ではなく「私はこう思う」「私たちはこんな失敗から学んだ」のように語りかけるスタイルを心がけましょう。
綺麗ごとや成功体験ばかり語らない
ひと目を気にし過ぎたり、炎上を恐れすぎたりするあまり、表面的な成功や綺麗ごとばかりの投稿では社長の魅力は伝わりません。
時には失敗談や、言える範囲で構わないので抱えている課題についても投稿しましょう。
-
その人だけが持つ言葉
-
実体験から導かれた想い
-
成し遂げたい未来と現実とのギャップで苦労していること
継続する
発信は一度や二度で効果が出るものではありません。
理想は週1本以上のコンテンツ発信です。
難しければまず隔週のペースでも構いませんので、継続して発信する習慣をつけましょう。
頻度が必要な理由は、ユーザーが社長の発信に触れる頻度が高いほど高感度が高まるからです。
ザイオンス効果といって、頻繁に接点があると好意的なイメージを持つ習性が人にはあるため、一定以上の頻度はとても有効なのです。
プロのサポートを活用する
文を書くのが本当に苦手だったり時間が取れない社長は、広報や編集のプロにサポートを依頼するのも一手です。
社内に広報担当者やライターがいれば対話しながら文章化してもらう、あるいは専門のコンサルタントに初期運用だけ伴走してもらうのも良いでしょう。
外部の視点が入ることで客観性が増し、「伝わる言葉」になりやすくなります。
チャコウェブも社長の言葉を発信するサポートや代行をしていますが、やりたいと思いつつなかなか踏み出せない忙しい社長には大変喜ばれています。
⚠️ 発信リスクへの向き合い方
発信を始めるにあたり、多くの経営者が心配するのが炎上リスクです。
「もし変な投稿をしてネットで叩かれたら…」
という不安は確かに理解できます。
ニュースではどうしても炎上した話題を取り上げられがちなので、よくあることのように思えますよね。
ただし過度に恐れる必要はありません。
基本的なリスク対策を押さえておけば、深刻な炎上はそう頻繁には起こりません。
-
公序良俗に反する発言や他者攻撃は絶対にしない
-
政治・宗教などセンシティブな話題は避ける
-
社外秘情報や個人情報の漏洩に注意する
-
高級レストラン・レジャー・ホテル等の話題には注意する
社長は立場上高級なお店などを利用する機会も多いかもしれません。
人によっては不公平感を煽ってしまい攻撃材料とされることもあるため、注意が必要です。
📌 まとめ
社長の発信は「仕事の延長」ではなく「経営そのもの」です。
トップ自らの言葉ほど会社を動かし、人の心を動かす原動力はありません。
最初は抵抗があるかもしれませんが、小さく始めて軽く仕組み化し続けてみましょう。
社長の声が社内外に届き始めたとき、採用にも営業にも思わぬ好循環が生まれるはずです。
そして、社長自身が発信することでしか得られない手応えや出会いがきっとあります。
ご意見・ご感想をお待ちしています!
このニュースレターに関するご質問やご意見がありましたら、ぜひお気軽にお知らせください。
あなたからの声をもとに、より役立つ情報をお届けしてまいります。
私が大切にしているのは、読者と共に成長していくこと。
私は上から下へと向かって「教授」していくのではなく、私自身が学んだことを「共有」していきます。
ですから、もし「こんなやり方が良かった」など、あなたの体験があったらぜひ共有していただけませんか?
「ここがうまくいかない」という悩みでも構いません。
有料サポートはこちら
ご登録いただくと、サポートメンバー限定のレターを過去回まですべてご覧いただけます。
価格はだいたいランチ1回分。
横山ゆみこが10年以上にわたって積み上げてきた経験とノウハウ、そしておびただしい数の書籍を基にした知識をわかりやすく、手ざわり感を大切にお伝えしていきます。
ウェブを活用しながら収益を上げる方法を共に学び、小さな会社発の素敵な世界にしていきましょう。
すでに登録済みの方は こちら