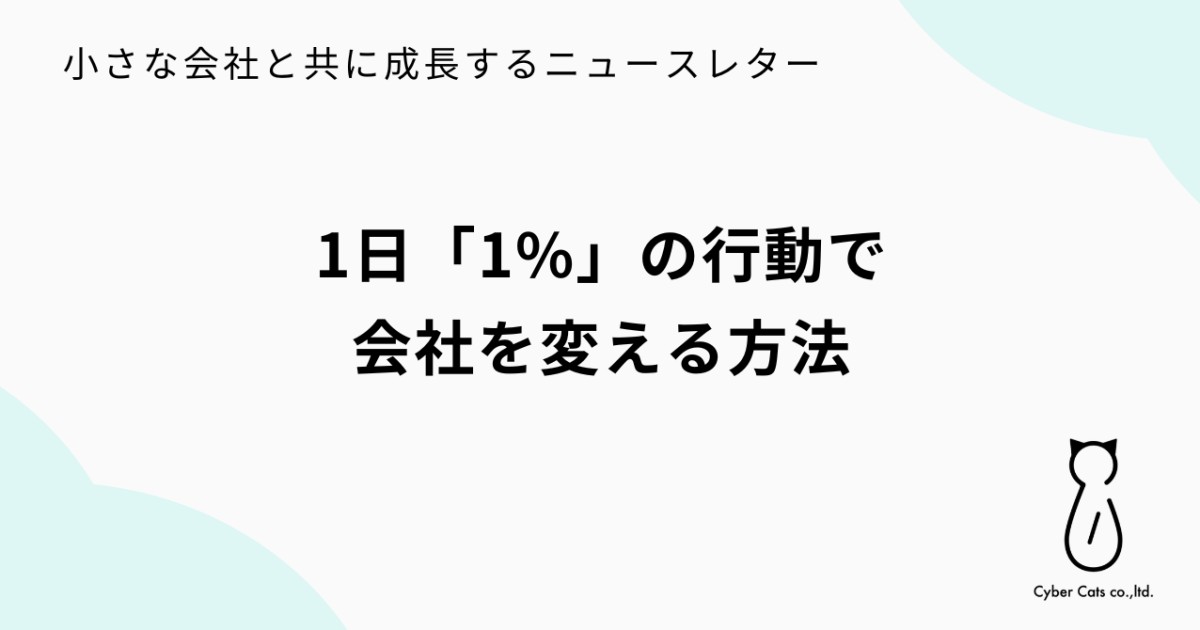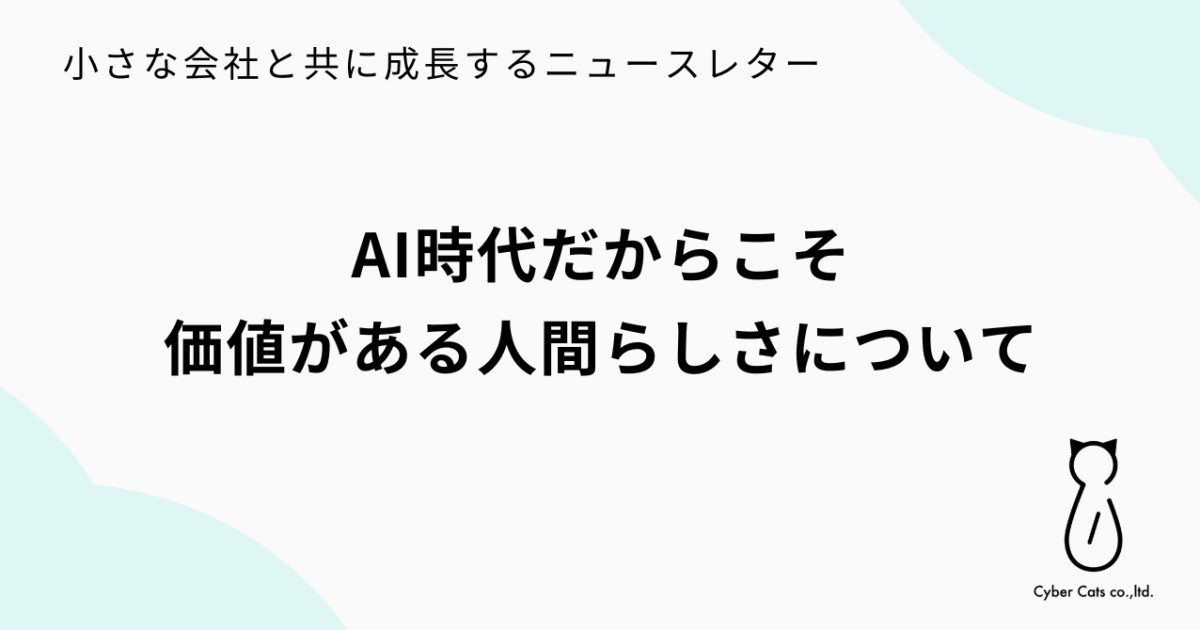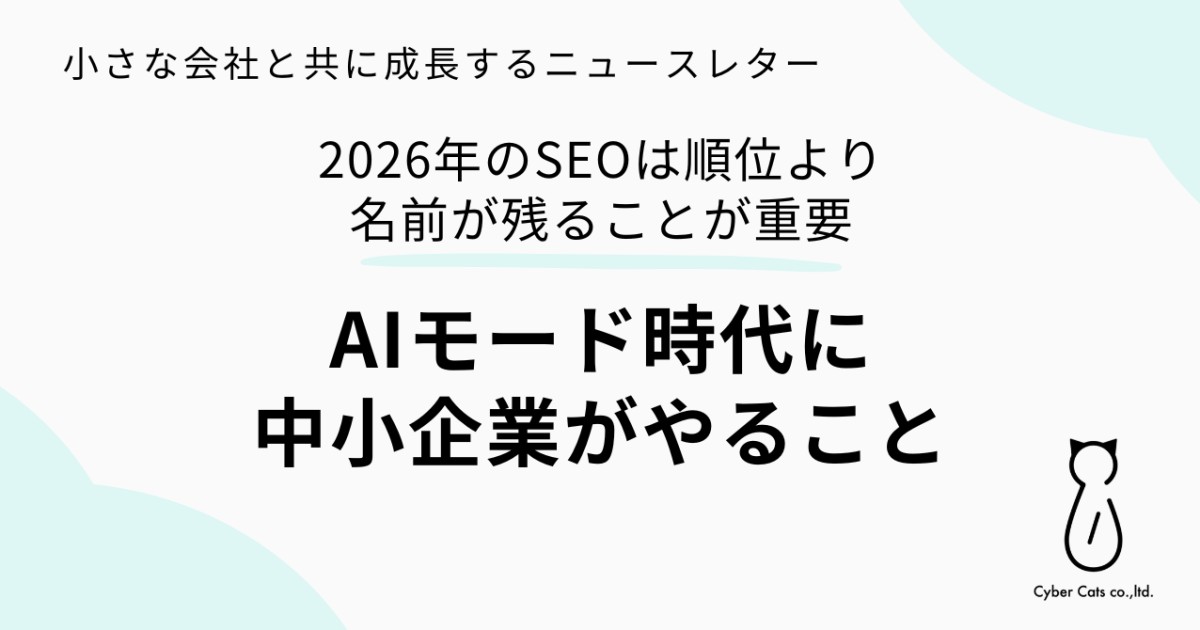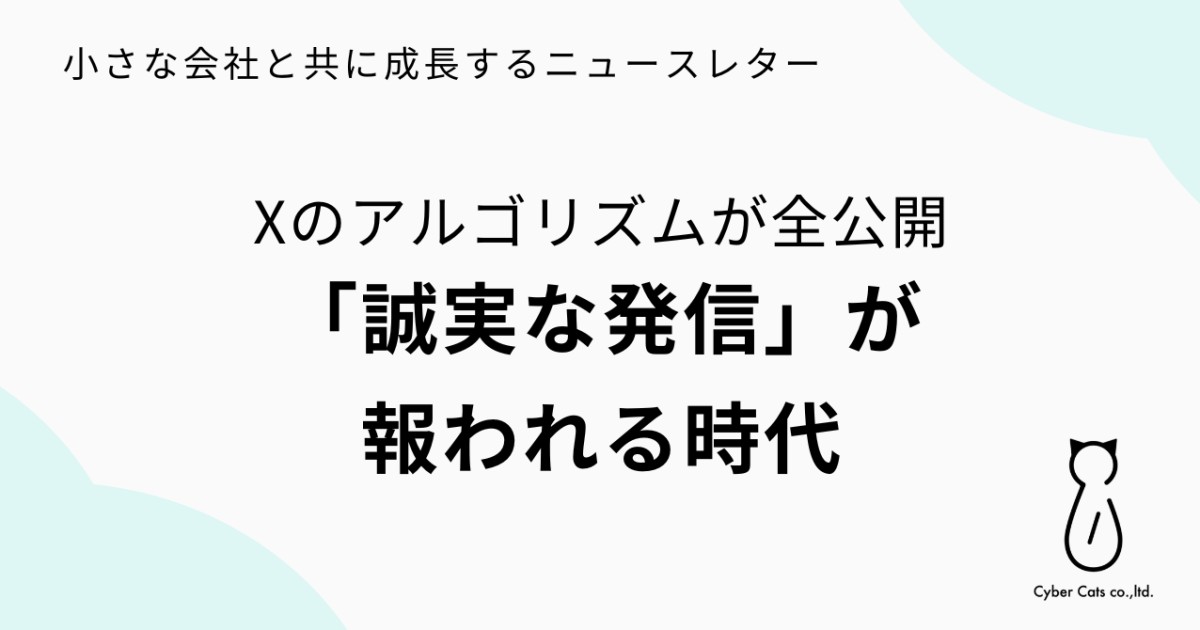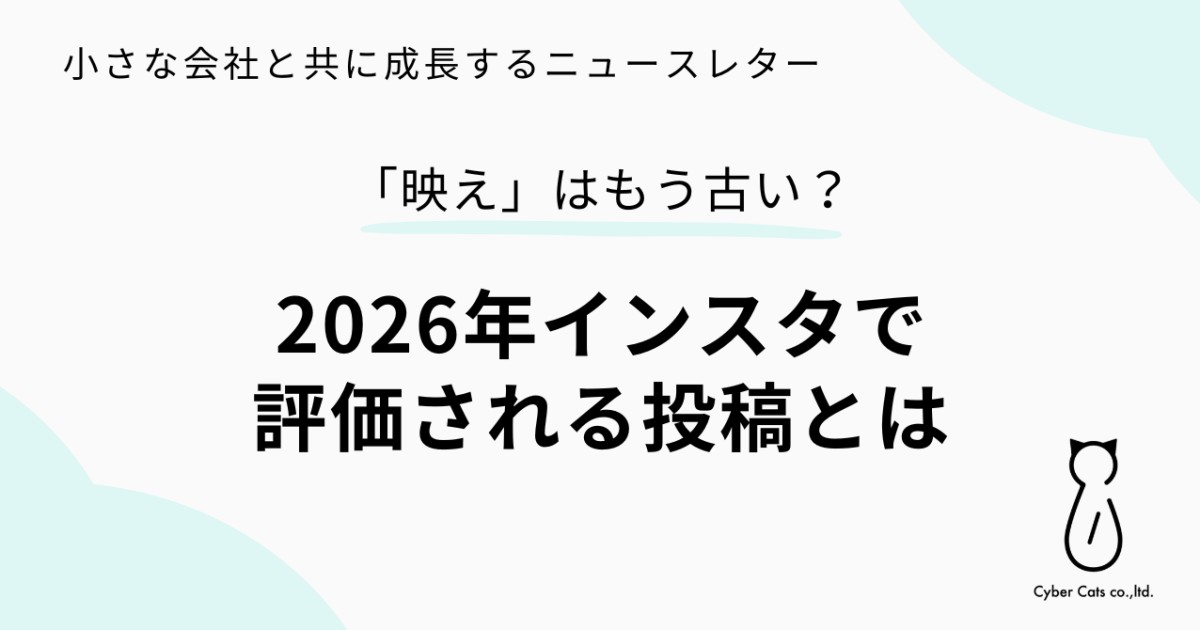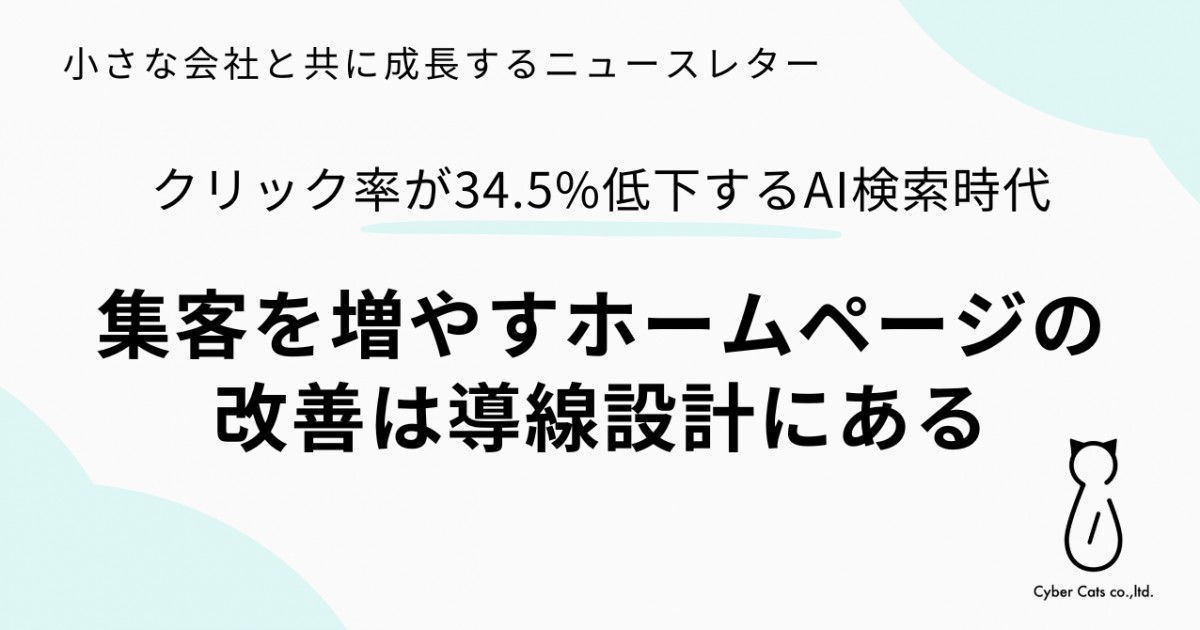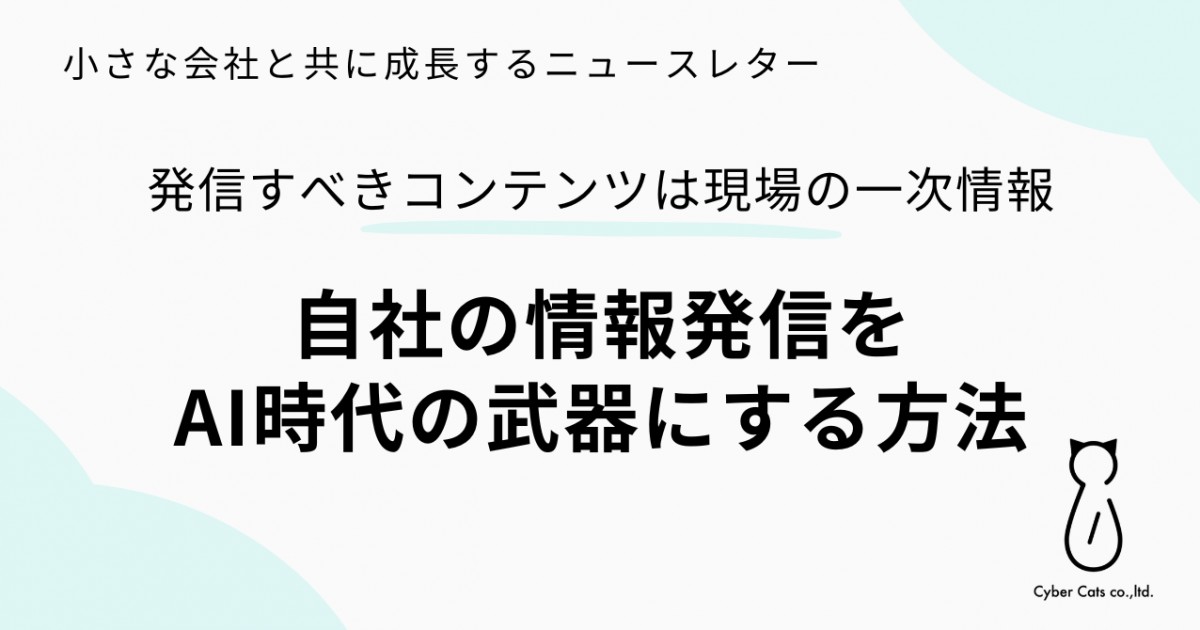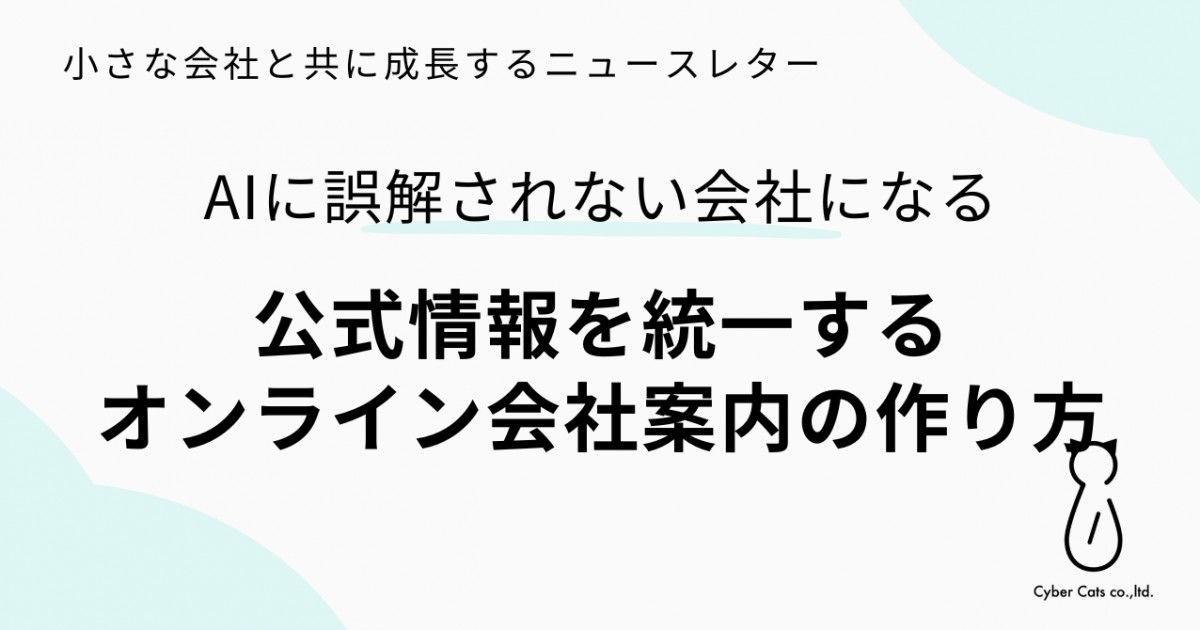AI検索やAI要約が普及する時代。ホームページは本当に必要なのか?
こんにちは、チャコウェブの横山ゆみこです。
皆さん、AIとはどのくらい付き合っていますか?
いろいろな方とお話をしていると、利用する度合いはさまざま。
とはいえ、日常の気付かぬところでAIが入り込んでいる場面はビックリするほど増えました。
今後、減ることはないでしょう。
情報収集に関しては、より顕著にAIの影響が出ています。
生成AIを活用した検索(いわゆるAI検索)や要約サービスが普及し、人々の情報収集行動は変化しつつあります。
検索エンジンで質問すれば、そのまま検索結果の画面上で答えを得られるようになりましたよね。
Google検索の「AIモード」や「AIによる概要」で、検索結果に表示されていても、ホームページにアクセスする数は減っていると言います。
「もはやホームページは不要なのでは」
「SEO(検索エンジン対策)は無意味になったのでは」
そのような声が出るようにすらなっています。
しかし、どんなにAI検索が便利になっても、企業や施設の「公式ホームページ(コーポレートサイト)」は基盤として不可欠な存在です。
今回は「AIが普及してもホームページが重要な基盤」である理由と、今後のホームページはどのような存在であれば良いのかについてみていきます。
目次
🏠 公式ホームページが持つ意味と信頼性とは
🔗 公式ホームページがないと、信頼構築が他メディアに依存することになる
🤖 AIは公式ホームページを参考に情報を入手する
📈 指名検索の需要も増える
🎯 指名検索で選ばれると質の高いアクセスが集まる
📰 一次情報の発信地として、ホームページを伸ばす
⚖️ YMYL領域はより正確な情報発信が求められる
💡 AI時代は、ホームページを含めた「オンライン情報」が重要になった
🧭 人とAIに情報が伝わるホームページのチェックポイント15
📌 まとめ
🏠公式ホームページが持つ意味と信頼性とは
AI時代においても、公式ホームページは企業・組織の信頼の拠り所です。
Googleの検索品質評価でも強調されるE-E-A-T(Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性))において、公式ホームページはそれらを示す最前線の場となります。
公式ホームページは、組織の一次情報(自社ならではの公式な情報)の発信源です。
他のメディアでは得られない独自の情報を出すなら、ホームページがベストと言えるでしょう。
かつては、テレビや新聞などに取り上げられるしか「発信源」はないような時代でしたが、自社が「公式」として「発信源」となれるホームページには、大きな価値があります。
🔗公式ホームページがないと、信頼構築が他メディアに依存することになる
逆に、公式ホームページがない状態を考えてみましょう。
この場合、自社が発信源になる場を持たないため、どこか別のメディアが発信するものに自社情報の信頼性を任せることになります。
例えば、業界のまとめサイトや比較サイトなどです。
これらのメディアに依存すると、よくこんなトラブルがあります。
-
載っている情報が間違っている
-
訂正の依頼を出しても対応してもらえない
-
広告を支払う企業を優先されるため、自社情報を見つけてもらえない
-
自社が発信したい内容と掲載される内容が食い違う
「間違って載せてあるので、修正してもらいたいのですが対応してらえません」
私にもよくご相談をいただきます。
この解決方法は2つあります。
-
修正依頼を出す
-
自社ホームページの存在感を出して正しい情報を参照してもらう
まとめサイト等の情報が間違っている場合、運営に連絡をして対応してくれることもありますが、無反応で誤った情報のままになるケースも少なくありません。
このような場合、自社ホームページがしっかり正しい情報を発信すれば、参照されて情報が訂正されていくことが多いものです。
そもそも、自社ホームページを持っていれば、そちらの情報を参照しますよね。
これは、AIでも同じなのです。
🤖AIは公式ホームページを参考に情報を入手する
冒頭で述べた通り、AIによる検索回答が普及したことで、人々の検索行動には変化が起きています。
Google検索の「AIモード」や「AIによる概要」は質問に対する回答や要約を検索結果画面ですぐに表示してくれるため、検索したユーザーはその場で疑問を解決できるケースが増えています。
そのため、一般的なキーワード検索からサイトへの流入は減少傾向にあります。
生成AIが回答を出す際に参考にしているのは、公式見解として信頼できる情報源を重点的に見るようです。
つまり、公式ホームページの情報は、その企業が「公式」の立場で発信するため参照されやすいのです。
AIに「おすすめの店を探して」のように、商品・サービスを探す質問を投げかける際は、より具体的なニーズを細かく伝える傾向があります。
そこで、AIに進めてもらうと、その人は商品・サービスを実際に利用するようになります。